民法等3−3 借家権(借地借家法)
借地借家法の適応を受ける建物に関する賃借権のこと
建物を借りて住む、賃貸住宅に住むことに関する規定
(例)
家の所有者A、借家人BAの家を借りているBは借家人
Bの持つ「生活に関わる家を借りる権利」が「借家権」
※借地借家法は、借家人を保護するために定められている
※夏季の貸別荘、展示会場などの明らかに一時的な使用目的の建物の賃貸借は、保護の必要が低いので、借地借家法は適応されない
※タダで貸す使用貸借も借地借家法は適応されない
定期建物賃貸借
契約の更新がなく、当初の存続期間が満了すると確定的に終了する借地権のこと
契約が終了したら必ず明け渡しとなる
契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要
契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければならない
貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となる
居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借り主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借り主から解約の申し入れができる
※この場合、解約の申し入れの日から1ヶ月が経過すれば契約終了
※この解約権が行使できるのは、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借り主限定
(中途解約に関して個別に特約を結ぶことは可能)
契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借り主に契約が終了することを通知する必要がある
(貸主と借り主が合意すれば、再契約することは可能)
定期借家制度は、平成12年3月1日から施行されている
それより以前に締結された住宅の普通借家契約は、借り主を保護する観点から、借り主と物件が変わらない場合、当分の間、定期借家契約への切り替えは認められていない
1 存続期間を定める場合
(1)存続期間
存続期間は民法の規定では→50年
借家に関してはこの民法の規定は適応されない→50年を超えることができる
(60年、70年と定めれば、そのようになる)
※1年未満の短い期間を定めた場合
期間の定めのない賃貸借契約とみなす
(定期借家の場合は覗く)
(2)契約の更新
・契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、更新拒絶の通知等がないと、従前の契約と同一の条件で更新される
(契約期間については期間の定めのない契約となる)
・契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、家主が正当事由のある更新拒絶の通知等をしたが、借家人が使い続けている場合、家主が何も異議を述べなければ、そのまま更新される
・賃貸人(家主)からの更新拒絶には正当事由が必要
(借家人を保護するため)
2 存続期間を定めない場合
契約期間が決まっていない場合は、お互いからの解約申し入れによって終了する
・家主からの申し入れ
正当事由、6ヶ月の猶予期間が必要
・借家人からの申し入れ
民法が適応されるので、正当事由は不要、猶予期間は3ヶ月あれば良い
借地の場合、借地上の建物の借地権の譲渡・転貸について、所有者に代わる裁判所の許可の制度があったが、借家権にはそのような制度は無い
必ず、所有者(家主/賃貸人)の承諾が必要
※建物や家の場合、丁寧に扱うか雑に扱うか、借り手によって使用方法が異なるため、
家主が承諾したく無いものを、裁判所が代わって承諾するのは、家主に不利益だから
(例)
家の所有者A(賃貸人)
Aの家を借りているB(賃借人)
Bから家を借りたC(転借人)
AB間の賃貸借が期間満了や解約申し入れで終了する場合
転借人Cを保護する観点から、賃貸人Aは転借人Cに対して通知をしなければならない
AがCに対する通知をしなかった場合は、Cは家を出て行かなくても良い
AがCに通知をすると、6ヶ月後に、BC間の転貸借契約が終了する
・借家人(転借人も含む)が、家主の承諾を得て、エアコンなどの造作を取り付けた場合
借家契約が期間満了または解約申し入れによって終了するとき
借家人は家主に対して、造作したものを時価で買い取って欲しいと請求することができる
これが造作買取請求権
※定期建物賃貸借契約でもこの造作買取請求権は認められている
※造作買取請求権が認められるのは、期間満了と解約にでの終了に限定されている
※債務不履行で終了する場合は、造作買取請求権は認められない
??なぜ造作買取請求権が認められているのか??
⬇︎
借家人が投下した資本の回収のため
造作買取請求権を排除する特約は有効
もし賃借人が造作を取り付けたとしても、家主はそれを買い取りませんということ
??造作買取請求権を排除する特約は、借り手に不利となるのに、なぜ有効なのか??
⬇︎
造作買取請求権があるせいで家主が承諾してくれず、借り手が造作をつけられないことになると、それはかえって借り手の不都合になるため
(エアコンを設置できないなど、生活が不便になる)
※定期建物賃貸借契約でもこの造作買取請求権排除の特約の設定は認められている
A所有の家をBが賃借している
Aはこの家をCに売却した
Cはこの家に自ら居住したいと考えている
Bはどうすれば、Cに対して賃借権を対抗できるか??
⬇︎
Bは家の引き渡しを受けていれば、Cに対抗できる
すでに引き渡しを受けて住んでいる状況であれば、退去しなくても良い
・BはAから土地を借り、そこに家を建てている
Bがその家をCに賃貸した場合、土地の利用権の譲渡・転貸になるか??
⬇︎
土地の利用権の譲渡・転貸にはあたらない
※Cは単に家を借りて住むだけであり、借地人Bと別に独立して土地を使用する訳では無い
・Bの借地権が存続期間の終了によって消滅するとき、Cは退去しなければならないか??
⬇︎
・Cが期間満了の事実を、その1年前までに知っていた場合
明け渡しをしなければならない
・Cが期間満了の事実を、その1年前までに知らなかった場合
Cは裁判所に請求をして、Cがそのことを知った日から1年以内の範囲で、土地の明け渡しに相当の期限を得ることができる
(引っ越しをするための猶予を得ることができる)
※Bの借地権が定期借地権であった場合でも、Cは上記と同様のことができる
・借家人が、相続人なしに死亡した場合
事実上の夫婦or養親子にあった同居者は、借家人の権利義務関係を引き継ぐ
※内縁の妻のような同居人を保護するため
※これに反する特約でも有効
(内縁の妻や養親子には権利義務を引き継がないという特約)
・内縁の妻などが、家を引き継がずに出て行きたい場合
内縁の妻などは、相続人なしに借家人が死亡したことを知った時から1ヶ月以内に、
家主に対して反対の意思表示をすれば、承継しない
契約は、公序良俗に反しない限りは原則自由だが、どんな内容でも売主買主間で自由に取り決めできるというわけでは無い
・任意規定
売主買主間で任意に取り決めた事項を、特約で契約すること
・強行規定
不動産取引において、知識の差は大きい
プロである不動産業者が売主、一般消費者が買主となる契約の場合、
売主に有利となる契約を、買主が契約書に記名押印したから全て有効だとすると、買主に不利益が生じる可能性がある
これを防ぐために、法律に反する契約は無効となる
この仕組みが強行規定
・不動産取引での強行規定
宅建業法や借地等での契約であれば借地借家法で強行規定の条項が定められている
宅建業法や借地借家法は特別法であり、その条文の中の規定に反する取り決めは無効とされている条項がある
※定期建物賃貸借の更新規定の排除を除く
※存続期間、更新、譲渡・転貸、借家権の対抗要件、借地上の建物の賃貸借などに関する借地借家法の定めよりも借家人に不利な特約は無効
※造作買取請求権は強行規定ではない
※居住用建物の賃貸借の承継も強行規定ではない
・更新がない借家権
・利用目的の制限もない
※更新がないので、一定期間がたてば確実に出て行ってもらえる、家主は貸しやすいし、家賃の変更もしやすい
1 定期建物借地権
(1)
期間の定めが必要
期間は20年でも1年未満でもOK
(普通の借家契約と異なり、6ヶ月と決めれば6ヶ月になるということ)
(2)
契約は必ず書面で行う
更新がないという重大な決まりがあるため、行き違いのないように書面が必要
※公正証書である必要はない
(3)
賃貸人は、契約を締結するにあたって「更新がなく一定期間が経てば借家契約が終わる旨を記載した書面」を使って説明する必要がある
この書面がない場合は、「更新がない」旨の定めが無効となる
=更新が認められる普通の借家契約になる
※この書面は契約書とは別で、独立した書面で用意しなければならない
※借家契約全体が無効になるのではないことに注意
※更新がないという契約が無効になり、更新が認めらるようになる
(4)
契約の終了にあたっては、家主から通知をしなければならない
期間が1年以上の定期建物賃借権の場合は、1年前から6ヶ月前までの間に家主の方から通知をする
この通知をしなければ、家主は終了を対抗できない
※賃借人が新しく住む家を探す必要があるため、期間が設定されている
(5)
賃借人が、転勤や療養などのやむを得ない事情で退去する時
・床面積が200㎡未満の居住用建物であること
・やむを得ない事情で借家を本拠地として使用できないこと
この2点に該当すれば、賃借人の方から中途解約をすることができる
(6)
(4)と(5)に反する内容で、借家人に不利な特約は無効
2 取り壊し予定建物の賃貸借
契約や法令によって、一定期間が経てば取り壊される予定のある建物の賃貸借
(契約→定期借地上の家など)
(法令→土地区画整理事業の区域内の家など)
・取り壊す時に契約が終了する
・取り壊す事由を記載した書面で締結する
地代や家賃を増額する、減額する請求については、借地と借家の両方でほぼ同じ内容
(1)経済事情の変動で土地の価格が不相応になった場合
当事者は、将来に向かって、地代や家賃の増額や減額を請求することができる
・一定期間増額しない旨の特約がある場合
その期間は増額の請求はできない
・一定期間減額しない旨の特約がある場合
減額の請求は可能
(2)増額、減額の金額の決定
増額請求
・家賃1ヶ月10万円の契約をしている場合
家主→15万円に増額したい
借り手→12万円が妥当だろう
この場合、借主は12万円を支払えば足りる
しかしその後の裁判で15万円と決定した場合は、
増額請求が行われた時点以降分の家賃が増額されることになる
・12万円しか支払っていなかった場合に借り手が支払う金額
1ヶ月あたりの不足分3万円×月
年1割の利息
この2つを合わせて支払う
※減額請求の場合は、増額請求の逆
※家主が借り手に返還する
民法等3−2 借地権(借地借家法)
法的弱者である借主を保護するために、民法よりも手厚く保護できるように定められた法律
※民法では契約は原則自由だが、不動産賃借は生活の基盤であり、弱者の借主が不利な契約をさせられることを防ぐ目的で定められている
借地権とは、、、
建物の所有を目的とした地上権と土地賃借権の2つのこと
(使用賃借は含まない)
・実際に建物を建てる人と土地を保有している人が違うときには、「借地権」を設定する必要がある
・借地権が設定された土地に建物を建てると、土地は土地を所有する人の物、建物は建てた人が所有する物という法的な区別がしっかりとできることになる
・臨時使用などの一時的な使用のために設定されていることが明確な場合
一定の借地借家法の定め(存続期間・更新・再築・更新拒絶の場合の建物買取請求権など)は適用されない
※短期使用の場合は、借地人保護の必要性が低いため
借地権設定者→ 土地の所有者
借地権者(借地人)→土地を借りた人
・地上権
他人の土地で建物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利のこと
地上権は、土地の賃貸借契約よりも強い権利
第三者への譲渡、転貸
地上権を設定した借主は、地主の承諾を得なくても地上権を登記して第三者に譲渡したり、賃貸したりすることが自由にできる
(土地に対して強い権利を持つ)
地上権の登記
借地権の所有者が地上権を希望した場合、地主は地上権の登記に応じる義務がある
登記簿には、地上権設定と記載される
登記簿を見れば地上権が設定してある物件であることがすぐに分かる
地代、賃料
地上権は地代を払わない契約でも成立するが、実際には地代を払う契約がほとんど
存続期間
地上権は永久とすることも可能
・土地賃借権
土地の賃貸人の承諾を得た上で、土地を間接的に支配する権利のこと
建物の利用目的が終われば、土地を土地の所有者に返すことが前提の契約
建物の改築やリフォームなど、耐用年数を伸ばす行為を行うときには地主の許可を得なければならない
第三者への譲渡、転貸
第三者への譲渡や賃貸をするときは、地主の承諾が必要
土地賃借権の登記
地主の承諾が必要
地主には登記の協力義務はない
(借地権者が所有する建物の登記をすれば、貸借権と同様の権利が得られるため)
地代、賃料
貸借権は必ず賃料の取り決めが必
存続期間
・民法上の存続期間
存続期間の設定は20年が限度(都度更新をすることができる)
期間の定めのない契約の場合、解約申入れ後1年で終了
・借地借家法上の借地権の存続期間
下記に記載
※宅建試験では、民法の規定ではなく、借地借家法の規定で回答する
※地上権は「物権」 土地の賃借権は「債権」
物権は誰に対しても権利を主張できる(そのものに対しての権利を持っている)
債権は土地の所有者に対してのみ権利を主張できる(契約内容のみに権利を持っている)
この性質の違いから、上記のような違いが生まれる
※地上権と土地賃借権、実際に採用されるのは??
土地賃借権の採用が多い
地上権は、土地の所有者がいても、その土地の上に建てられている建物部分の支配権はほぼ地上権所有者が持つことになり、土地の所有者に対しては不利な面が多すぎるため
賃借権の場合、土地の所有者が変わったとしても、その建物を登記していれば貸借権は有効なので、賃借権の方が両者にとって不便が少ない
※では地上権はどのような場合に設定されるのか??
土地の上に建物が建っていて、さらにその上に鉄道の高架や高速道路が建てられたり、地下には地下鉄が走っていたりする場合がある
このような高架の鉄道や高速道路、地下鉄線路などに地上権が設定されていることが多い
地上権を持つことで、土地を所有しているのとほぼ変わらない権利になるため、鉄道や道路の補修なども土地の所有者の承諾を得なくても、鉄道会社などが独自の判断で補修を行うことが可能になる
借地借家法における借地権と借家権の違い
借主を保護する必要があるなら「借地借家法」において、借地と借家の双方に同じ制度を設ければ足りるとも考えられる
しかし実際は、借地と借家の両者は異なる内容の法律となっている
??なぜか??
⬇︎
借地、借家共に借主保護の必要があるが、その保護の必要性の程度が異なる
借主が無理やり追い出された場合の比較
・借家の場合
次に移るべき建物を探し、そこへ引っ越しをすれば足りる
・借地の場合
何も建っていない土地(更地)を借り、そこに建物を建てて住んでいた場合は、その土地を返す際に、元通りの更地にして返さなければならない
借主は次に移るべき建物を探して引っ越しをし、さらに、わざわざ建てた建物を壊さなければならない
建てた建物が無駄になり、かつ、壊す費用がかかるため、借地人の不利益が大きい
⬇︎
借家人に比べ、借地人の方をより保護しなければならない
借地の方がより保護されるように、借地と借家で異なる制度を設けている
・最短期間が定められている
当初の存続期間 最短30年間
最初の更新時 最短20年間
2回目以降の更新時 最短10年間
借地権は建物の所有が目的のため、一定の長い期間の存続が必要
期間を定めなかった場合、自動的に上記期間となる
当初の存続期間を設定する際に、当事者同士で最短期間よりも長い期間を設定することができる
(例)
当初の存続期間を40年と定める→期間は40年
当初の存続期間を20年と定める→期間は30年
※借地権では必ず期間が定まるので、特約ない限り、中途の解約申し入れは不可
??更新時の20年や10年の期間は、両者の合意で長く設定できる??
⬇︎
できる
・最短期間が定められている
最初の更新時 最短20年間
2回目以降の更新時 最短10年間
1 合意更新
合意の場合は上記の通り、最初の更新は20年よりも長い期間、2回目以降の更新は10年よりも長い期間で定める
※借地人の保護を図っている
2 請求による更新
請求による更新の場合も上記の通り、最初の更新は20年よりも長い期間、2回目以降の更新は10年よりも長い期間で定める
※借地人の保護を図っている
・建物が現存する場合に限る
建物がない状態では更新する意味がないため
・借地権者(借地人)は
期間満了の際に、借地権設定者に請求すれば更新される
・借地権設定者は
期間満了の際に、借地人に対して契約打ち切りを、遅滞なく異議を述べることができる
ただし正当事由がなければ、この異議は認められない
※この場合の正当事由とは
借地権設定者と借地権者、転借地権者が土地を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過、土地の利用状況、立ち退き料などの借地権設定者が土地の明け渡しの際に支払うべきものがあるかと言った、様々な事情を総合的に考慮して判断される
※正当事由が認められやすい場合
借地権設定者がその土地を必要としている度合いが高い場合
(期間満了した以上、借地権設定者が土地を必要としていれば、更新を認めるべきではないから)
借地権設定者が借地権者に対して立退料を支払うといった申し出がある場合
(借地権者に有利)
3 法定更新
法定更新の場合も上記の通り、最初の更新は20年よりも長い期間、2回目以降の更新は10年よりも長い期間で定める
※借地人の保護を図っている
・法定更新とは
賃貸借の期間が終わっても建物があるので、借地権者がそのまま土地を使い続けていた場合に、借地権設定者からの正当事由ある異議がない場合は、自動的に更新される
これが法定更新
・建物が現存する場合に限る
建物がない状態では更新する意味がないため
・最短期間が定められている
当初の存続期間 最短30年間
最初の更新時 最短20年間
2回目以降の更新時 最短10年間
1 最初の契約期間中の再構築
賃借人B(借地権者)は土地の所有者A(借地権設定者)から
建物所有の目的で期間30年として土地を借り、家を建てていた
25年経過した時点でその家が滅失した場合どうなるか??
⬇︎
建物が25年目で滅失した場合、契約期間は後5年残っている
賃借人Bが家を再築した場合に、後5年しか住むことができないのはBに不利
⬇︎
・土地の所有者Aの承諾を得て再築した場合
Aの承諾のあった日
建物が再築された日
この2つの日のどちらか早い日から、原則として、契約は20年間存続する
※BがAに対して「再築します」と通知を出して2ヶ月たってもAからの異議がなければ、承諾があったと見なされる(承諾の擬制)
2 契約更新後の再構築
賃借人B(借地権者)は土地の所有者A(借地権設定者)から
建物所有の目的で期間30年として土地を借り、家を建てていた
初回の更新をして、存続期間は20年延長されている
その時点でその家が滅失した場合どうなるか??
⬇︎
契約を更新した後に、借地上の建物が滅失し、それを再築した場合
土地の所有者Aの承諾がある場合
借地権者Bは再築、地上権の放棄、土地の賃貸借の解約申し入れを選択できる
(Bは30年以上住んでおり、再築しない場合もある)
再築したら→20年間期間が延長される(最初の更新と同じ)
土地の所有者Aが再築を承諾しない場合
借地権者Bは裁判所に申し立てをして、Aに代わる裁判所の許可を得れば、再築による期間が原則として20年の延長が認められる
※裁判所はこれと異なる期間を定めることができる
(絶対に20年延長されるわけではない)
※更新後の再築は、前述の1と異なり、通知による承諾の擬制は認められない
土地の所有者Aが再築を承諾しておらず、Bが裁判所の許可を得ずに無断で再築した場合
AはBに対して、地上権の消滅請求か土地の賃貸借の解約申し入れができる
解約の申入れから3ヶ月の経過により契約は終了する
※Aが解約申入れをしなかった場合、借地権は本来の存続期間を変えず存続期間中有効となる→20年間継続される
借地権設定者→ 土地の所有者A
借地権者(借地人)→土地を借りた人B
転貸人/譲受人→Bから土地を転貸/譲受たC
(1)
AB間の借地契約の後、Bは借地上に建物を建てた
Bはその建物をCに譲渡した
この場合、建物は土地の利用権がないと存続できないので、借地上の建物を譲渡するときは原則として、借地権も同時に移転する
(2)
・借地権が地上権の場合
Aの承諾がなくてもBはCに借地権を譲渡できる
譲渡や転貸には制限がない(地上権は強い)
・借地権が土地の賃借権の場合
賃借権の譲渡・転貸にはAの承諾が必要
・土地の賃借権でBはCに建物を譲渡・転貸したいが、Aが承諾をしない場合
特に不利益がないのにAが承諾をしない場合、Bは裁判所の許可を得れば、譲渡・転貸できる(Aの承諾の代わりに裁判所の許可を得ればOK)
(3)
・競売や公売における土地賃借権の譲渡の場合
不利益がないのにAが承諾をしないときは、競売や公売によって取得した者が、Aの承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができる
この申し立てができるのは、競売人等が建物の代金を支払った後、2ヶ月以内に限られる
借地権設定者→ 土地の所有者A
借地権者(借地人)→土地を借りた人B
転貸人/譲受人→Bから土地を転貸/譲受たC
1 契約の更新拒絶の場合の建物買取請求権
Aに正当な事由があり契約が更新されない場合
借地権者Bは期間満了の際に、Aに対して建物を時価で買い取って欲しいと請求することができる
これが建物買取請求権
※Bが投下した資本の回収、社会経済上の損失の防止を目的として定められている
Bの債務不履行によって契約が終了する場合
買取請求はできず、Bは自身で建物の撤去をすることになる
2 第三者の建物買取請求権
CはBから建物を譲り受けたが、Aが土地の賃借権の譲渡・転貸を承諾してくれない
CはAに対して、購入した建物を時価で買い取って欲しいと請求することができる
※この場合のAに対する買取請求は、譲渡人Bではなく譲受人Cが行う
1 建物の登記
AがBに土地を貸し、Bがその上に建物を建てて使用している
土地所有者のAが、この土地をCに譲渡した場合
・民法では
賃借権の登記があれば、Bは土地を使い続けられるとしている
・賃貸借の場合
地上権とは異なり、土地所有者Aは賃借人Bの登記に協力する法律上の義務はない
(Bの登記をしてしまうと、Aの土地の値段が下がりかねないため)
Bは借地権の登記を備えることができず、追い出されることになる
(現実では、民法の規定ではなく借地借家法の規定が適用されるため)
借地借家法では、このBの保護を図るために、借地権者Bは借地上に登記した建物を持っていれば、その借地権を対抗することができる
この登記はBの建物の登記のため、Aの協力は不要
Bは1人で登記ができる
※表示に関する登記は対抗力がないのが原則
しかし判例では、この借地上の建物の登記は、表示に関する登記でも良いとされている
(弱者である借地権者の保護のため)
※判例では、その建物の登記名義人と借地権者は同じ名義でなければならないとしている
建物の登記が息子名義や妻名義では、登記した建物を持っていることにはならない
Bはかつて、借地上に自分の建物を建てて、それを自己名義で登記していた
その建物が火事で焼失し、Bは借地上に登記した建物を無くしてしまった
その間に土地を買ったCから待機を求められた場合、Bは出ていかなければならない
こういった場合に、Bを保護するために、掲示による保全が認められている
Bは土地の見やすい場所に、再築する旨などの一定の事項を掲示(看板を立てる)しておけば、2年間は、新たな譲受人Cに対抗できる
※対抗力が認められるのは、もともと建物の登記がされていた場合に限る
(1)
建物の種類・構造・規模などを制限する借地条件がある場合で、
事情の変更で、従来の借地条件と異なる建物を所有するのが適当であるにも関わらず、
その変更について当事者間に協議が調わないときは、
裁判所は当事者の申し立てにより、その借地条件を変更することができる
(2)
借地権者が既存の建物について、建物の種類を同一のまま増改築することは、
その禁止の特約がない限り、土地所有者の同意なしで、自由に行うことができる
※増改築禁止の特約がある場合
土地所有者の承諾がないと増改築はできない
土地の通常の利用上相当な像界V引くについて、当事者に協議が整わないときは、
裁判所は借地権者の申し立てにより、その増改築について土地所有者の代わりに承諾を与えることができる
(1)一般定期借地権
存続期間 50年以上
目的 自由
要件 公正証書等書面による更新等を排除する旨の特約
建物利用 ・建物買取請求権は排除される
・借地人の建物利用は継続されない
消滅 更新がなく期間の満了か建物の土地所有者への譲渡によって借地契約終了
(2)事業用定期借地権
存続期間 10年以上50年未満
目的 事業用の建物所有目的のみに限定(居住用は不可)
要件 公正証書による設定契約が必要
建物利用 ・建物買取請求権は排除される
・借地人の建物利用は継続されない
消滅 更新がなく期間の満了か建物の土地所有者への譲渡によって借地契約終了
※賃貸住宅事業者が賃貸マンションを建てることはできない
※従業員の居住用の社宅を建てることはできない
※必ず公正証書が必要、それ以外の書面ではダメ
(3)建物譲渡特約付借地権
存続期間 30年以上
目的 自由
要件 30年以上経過の後建物を土地所有者に譲渡する旨の特約
建物利用 借地人の建物利用は原則として継続されない
消滅 更新がなく期間の満了か建物の土地所有者への譲渡によって借地契約終了
※上記の特約により借地権が消滅した場合
その借地権者(または建物の賃借人)で、
権利が消滅した後もなお建物の使用を継続している者が請求したときは、
請求の時に、その建物につき、その借地権者(または建物の賃借人)と借地権設定者との間で「期間の定めがない賃貸借」がされたものと見なされる
※借地権者が請求をした場合において、借地権の存続期間があるときは
「その残存期間」=「存続期間」となる
民法等3−1 賃貸借契約
・賃貸借契約
家賃(賃料)を支払い部屋(目的物)を借りるといった契約
借りる側を「賃借人」
貸す側を「賃貸人」
賃貸契約によってそれぞれに義務(債務)が生じる
(貸す側の義務)
1:目的物を賃借人に使用させる
2:目的物を修繕する
3:費用の償還(賃借人が立て替えた費用を返還する)に応じる
・自分が賃借人の立場で契約をしてアパートに住み始めた場合、、、
もしトイレの水が流れなかったりしたら生活に支障が出てしまうので
すぐに修繕する必要がある(必要費)
・もしそのトイレを賃借人自身が実費で修繕した場合、、、
そもそもそれを直すのは賃貸人の義務なので
賃借人は必要な修繕にかかった費用の全額を賃貸人に対し”直ちに”請求できる
※賃借人の責めに帰すべき事由、賃借人の不注意や故意に何かを汚損破損した場合
賃貸人に修繕の義務、費用償還の義務は無い
※賃借人は、賃貸人が行う目的物の保存に必要な修繕行為を拒むことはできない
※賃借物の修繕が必要な場合で、急迫の事情があるときは、賃借人は自分でその修繕をすることができる
※有益費
そのものの値打ちを増すのにかかった費用のこと
(例)
賃借人が建物に対して修繕を行った結果、その建物の価値が増した
賃借人は賃貸人に対して、かかった有益費の償還請求ができる
償還請求するための条件
・賃貸契約終了の時に、その価格の増加が現存していること
・支出額または増価額のどちらか一方を請求できる
(どちらにするかは、賃貸人の選択に従う)
1:賃料を支払う
民法では、賃料は後払いが原則
宅地建物の場合は月末払いが原則
実際の不動産の賃貸実務では、ほぼ、特約をつけて家賃前払いにしている
2:目的物を返還する、また、返還の際の”原状回復”義務
・原状回復
借りた当初の状態に戻して返すこと
(例)
契約時には綺麗だったドアを、飼い犬がボロボロにしてしまった場合
賃借人がドアの修理代を支払い、綺麗に直してから返還しなければならない
※通常の使用によっての損耗や経年劣化については、賃借人はこの義務を負わない
3:目的物の善管注意義務(丁寧に扱うのが義務)
「善良な管理者としての注意義務」という意味
一般社会人として、取引の上で通常要求される程度の注意義務のこと
・期間に定めのない契約の場合
各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる
・期間が定められている契約の場合
その期間満了によって賃貸借が終了する
※期間に定めがあっても、契約書に「期間満了時の1ヶ月前までに解約の申し入れがなければ、自動更新とみなす」とした内容が記載されることもある
(一般的な賃貸マンションなどの契約では、自動更新になっていることが多い)
※当事者間の合意で契約を更新(継続)することも可能
もし、火事等で目的物そのものが「全部滅失」した場合、賃貸借契約は終了する
・賃借権の対抗要件は、賃借権の登記
(例)
Aの借りていた土地を、貸主であるBが、Cに売却した
・A→Bから土地を借りていた
・B→自分の土地をCに売却
・C→「Aは私の土地から出て行って」
この場合、土地の所有権はCに移る
Cが「もうここは私の土地なので、出て行ってください」と言ってきた場合、AがCに対抗するためには何が必要か??
⬇︎
「賃借権の登記」が必要
・Aが賃借権を登記していた場合
→Cの要求を拒むことができる
・Cが「所有権移転登記」をした場合
→Aに家賃の請求をすることができる
A→賃借権の登記をしているから出て行かないよ
C→わかりました、所有権移転登記をしたので、土地の使用料は私に払ってください
※所有権移転登記は法務局で確認できる
・賃借権が二重に譲渡されていた場合
不動産の賃借権が二重に設定された場合の優先関係も、賃借権の登記の先後で決定する
・賃貸人の地位の移転、主張
・賃借人に対抗要件が備わっている時
所有権の移転に伴って、賃貸人の地位は、旧所有者Bから新所有者Cに移転する
・賃借人に対抗要件が備わっていない時
賃貸人の地位は、賃借人の承諾なしに、譲渡人Bと譲受人Cの合意により移転させることができる
※賃借物を使用させるなどの賃貸人の債務は、所有者なら誰でも履行できるので、賃借人の承諾は不要
※賃貸人の地位を賃借人に主張する場合は、新所有者Cは、自身が新たな賃貸人であることを証明するために、所有権の移転登記が必要
(賃貸人の地位を主張するとは、、、賃料を請求するなどの権利の主張)
1 存続期間を定める場合
賃貸人と賃借人との間で賃貸借の期間を定める時、最長期間は50年
(60年で契約しても、期間50年の賃貸借になる)
※改正前は期間20年だったが、社会のニーズにより50年になった
※民法上、期間を定めた場合は、、、
賃借人は契約に定められた時期に建物の返還をしなければならない
中途解約もできない
(特約がある場合は、返還の時期が延長されたり、中途解約できることもある)
2 存続期間を定めない場合
・賃貸借契約は、いつでも、解約申し入れがあれば終了する
・土地の場合は、解約申し入れをして1年経てば終了する
・建物の場合は、解約申し入れをして3ヶ月経てば終了する
※賃貸人が「出て行け」と言う場合と、賃借人から「出ていきます」と言う場合、どちらも同じ3ヶ月
3 黙字の更新
契約期間が終了しても、借り手がそのまま使い続けている場合、賃貸人が何も異議を述べないなら、そのまま更新される
4 目的物の消失
目的物の全部が滅失して使用できなくなった
→賃貸借契約の場合は、契約は終了する
※賃貸借契約は、一定の期間人に物を貸し続ける継続的な契約
※目的物を貸すことができない状態なのに、そのまま契約関係が続いてしまうと、法律関係が複雑になるため
・賃借権の譲渡
賃借人が、賃借権自体を売買や贈与等によって他人に移転すること
(問)賃借権の譲渡
・賃貸人A、賃借人B、賃借人から賃借権を譲り受けたC
BはAの承諾を得て、賃借権をCに譲り渡した
(Bは賃借権をCに売却し、賃借権がBからCに移転した→賃借権の譲渡)
Aは賃借権の譲渡後に発生した賃料を、誰に対して請求できるか??
⬇︎
賃借権を譲渡した場合、Bは賃貸借契約の関係から離脱したことになる
AとCの間で、新たに賃貸借契約が発生する
つまり、譲渡後に発生した賃料などは、AはCに対して請求することになる
・賃借権の転貸
賃借人が、自己の賃借人としての地位を維持したまま、目的物を他人に賃貸すること
(又貸し)
(問)賃借権の転貸
・賃貸人A、賃借人/転貸人B、転借人C
BはA所有の家を賃借している
BはAの承諾を得て、適法にその家をCに転貸した
この場合のA、B、Cの法律関係はどのようになるか??
⬇︎
・BとCとの間で新たに賃貸借の契約が結ばれる→転貸借
BC間の転貸借では、Bは転貸人、Cは転借人
・転貸借の関係がある場合でも、BとAとの賃貸借関係は継続する
依然としてAは賃貸人、Bは賃借人のまま
※転貸借の場合はBは契約関係から離脱しない(賃借権の譲渡との違い)
※賃借権の譲渡も転貸も、 賃貸人の承諾を得なければ譲渡・転貸をすることはできない
(民法612条1項)
・承諾のある転貸借の場合、転借人のCは、賃貸人のAに対して、転貸人Bの債務の範囲を限度として、転貸借に基づく債務を直接に履行する義務を負う
(例)
賃貸人A、賃借人/転貸人B、転借人C
賃貸人AはBに7万円で家を貸している
BはCにその家を10万円で転貸した(転借人Bと転貸人Cの関係)
⬇︎
賃貸人Aは直接、転借人Cに対して賃料を請求できる
金額はAB間の賃料とBC間の賃料の、安い方が限度額となるため、AがCに請求できる賃料は7万円となる
AとCには直接の契約関係はないが、転貸によってAの財産が危険に晒される可能性があることから、Aの利益を守るために認められている
・賃借人/転貸人Bの債務不履行により、AB間の契約が解除された場合、Cは転借権をAに対抗できないため、AはCを追い出すことができる
転借人Cの権利は、賃借人/転貸人Bの権利を基礎としている
Bの立場が消える以上、CはAとの関係において不法占拠と同じ立場になる
・賃貸人Aが、賃借人/転貸人Bの賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除する場合、賃貸人は賃借人に対して催告すれば足りる
転借人に対して通知をする必要はない
賃借人に代わって賃料を支払う機会を転借人に与える必要もない
・賃貸人Aと賃借人Bの間で、賃貸借契約を合意解除した場合、賃貸人Aは、原則として、転借人Cを追い出すことはできない
AとBの関係によって、転借人Cの「目的物の使用収益」の利益が害されることが無いように、これが定められている
(問)正誤
AはBに対して甲建物を月20万円で賃貸し、
BはAの承諾を得た上で、甲建物の一部を、Cに対して月10万円で転貸している
この場合、賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、
転借人Cに通知して賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない
⬇︎
(誤)
賃貸人は賃借人に対して催告をすれば足り、転借人に対して通知をする必要も、賃料を支払う機会を与える必要も無い
賃貸人A、賃借人/転貸人B、転借人C
・BがCに無断譲渡、無断転貸をして使わせた場合
賃貸人Aは、原則として、賃貸借契約を解除することができる
(賃貸人と賃借人の信頼関係が失われるため)
※信頼関係が失われない特別な事情がある場合は、解除はできない
敷金とは、、、
・賃借人の賃貸人に対する金銭債務(賃料)を担保するために、賃借人から賃貸人に対して交付される金銭のこと
・賃借人に賃料の不払い等があった際の、賃貸人の担保となる
・契約が終了し、賃借人が建物を明け渡すときは、未払い賃料等を控除した残額について、賃借人の敷金返還請求が発生する
・賃借人が敷金返還請求をするためには、まず建物を明け渡さなければならない
(明け渡しが先、敷金の返還は後)
(明け渡しと敷金の返還は同時履行の関係とはならない)
・敷金は賃貸人にとっての担保のため、賃借人は賃貸人に対して、敷金を延滞賃料などの弁済に充てるよう請求することはできない
賃貸人A、賃借人B、新賃貸人C
AB間の賃貸借契約締結に際し、BはAに敷金を差し入れた
その後、AB間の賃貸借契中に、AはCに家を譲渡し、Cが新たな賃貸人となった
??Bは賃貸契約終了後、AとCのどちらに対して敷金返還請求をすればいいか??
⬇︎
Cに対して請求する
敷金返還債務は、Aに対する未払い賃料等を控除した残額について、AからCに移転する
※敷金は賃貸人の担保のため、賃貸人の地位が移転する場合は、担保も合わせて移転する方が効率的
賃貸人A、賃借人B、新賃借人C
AB間の賃貸借契約締結に際し、BはAに敷金を差し入れた
その後、AB間の賃貸借契中に、BはAの承諾を得て、賃借権をCに譲渡した
??この時、敷金に関する権利・義務は、新賃借人Cに承継されるか??
⬇︎
原則として、敷金関係はCに移転しない
敷金を受け取っているAは、敷金の額からAに対する未払い賃料等を控除した残額を、Bに対して返還する
・ 賃貸借
性質
有償、諾成契約
目的物の修繕義務
賃貸人には原則として修繕義務がある
費用の負担
賃貸人は賃借人に対して費用の償還を請求できる
必要費→直ちに請求できる
有益費→終了時に請求できる
貸主の担保責任等
売買の契約不適合(売主の担保責任)と同じ規定が準用される
賃借権の登記等
契約の終了
期間を定めた場合→期間満了時に終了
期間を定めなかった場合→各当事者はいつでも解約申し入れができる
目的物の全部滅失→契約は解除となる
債務不履行の場合賃貸借契約は解除される
借主の死亡
賃借権は相続人に相続される
・ 使用貸借
性質
無償、諾成契約
目的物の修繕義務
貸主に修繕義務は無い
費用の負担
借主は通常の必要費を負担しなければならない
貸主の担保責任等
使用貸借と同じ無償契約である贈与契約の規定(引き渡し義務)が準用される
なし
契約の終了
・期間を定めた場合
期間満了時に終了
・期間を定めなかった場合
※借主側は、いつでも解除できる
(1)使用・収益の目的を定めた時
①その目的に従って使用・収益が終わった時に終了する
②その目的に従い借主が使用・収益に足りる期間を経過した時は、貸主は解除できる
(2)使用・収益の目的を定めなかった場合
貸主はいつでも解除できる
借主の死亡
使用貸借契約は終了する
民法等2−9 弁済と相殺
契約の取り消し
契約の解除
時効
債権は消滅時効にかかるので、時効によっても消滅する
弁済
債務の履行が完了し、債権は目的を達成したので消滅する
代物弁済
債務の内容として指定されている給付の代わりに、他の給付をすることによって、債権を消滅させる行為
100万円の金銭債務を負っている債務者が、100万円の代わりに100万円相当の壷を債権者に給付することで弁済をするなど
供託
弁済者が、債権者のために、弁済の目的物を国家の一機関に寄託することによって、債務を免れる行為
更改
債権の要素である債権者・債務者・債権の目的物いずれかを変更することによって、
古い債権を消滅させ、同時に新たな債権を成立させる契約のこと
500万円の支払債権の目的物は500万円の金銭だが、
この目的物を500万円相当の壷に変更させることによって、
500万円の金銭債権を消滅させると同時に、
500万円相当の壷を引き渡してもらう債権を成立させる
※代物弁済→現実に代わりの給付が行われるの
※更改→内容を変えた新たな債権が成立するにとどまる
免除
債権者が、債務者のために、何の見返りもなく債権を消滅させる行為のこと
免除は、債務者の承諾を得ることなく単独で行うことができる
混同
債権と債務が同一人に帰属することで、両者を存続させておく必要がなくなり、債権・債務がともに消滅すること
500万円の債権者Aが債務者Bの父であり、後にAが死亡し、Bが唯一の相続人としてAの地位を相続した場合、Bは自己の債権者ともなり、自分に対して請求して自分に対して払うという状態になるので、債権と債務を存続させておく必要がなくなり、債権と債務は消滅する
相殺
二人が互いに同種の債権を有している場合において、その2つの債権を対当額において消滅させる意思表示のこと
弁済→債務の履行と同じ
お金を借りた者が「借りたお金を返すこと」は弁済
土地の売買契約をした売主が「土地を引渡すこと」も弁済
弁済できる人
本来は債務者がするもの
しかし、債務者以外の第三者でも弁済は可能
・第三者の弁済が認められない場合
1 債務の性質が、第三者の弁済を許さない場合(歌手のコンサートなど)
2 当事者間で第三者の弁済は不可の特約がある場合
3 弁済することにつき、正当な利益を有しない第三者による弁済で、一定の場合
・弁済することにつき、正当な利益を有しない第三者による弁済で、一定の場合とは
正当な利益を有しない第三者 → 友人や親族など
1 債務者の意思に反するとき
(債務者の意思に反すると、債権者が知らなかった場合、その弁済は有効)
2 債権者の意思に反するとき
(第三者が債務者から委託を受けて弁済をする場合、そのことを債権者が知っていたときは、その弁済は有効)
※債権者には拒絶権がある
見ず知らずの他人からの弁済を拒絶したい人もいるので、認められている
債務者の友人や親族が弁済をする場合は、債権者が承諾すればOK
(例)
債権者Aは債務者Bに100万円を貸している
??正当な利益を有しない第三者Cが債務者Bの代わりに100万円を弁済できるか??
⬇︎
債務者Bの意思に反する場合は、Cは弁済をできない
??Cによる弁済が、債務者Bの意思に反していると知らずに、債権者AがCからの弁済を受領した場合、この弁済はどうなるか??
⬇︎
債権者Aがそれを知らずに受領した場合、弁済は有効
??抵当権が設定されている不動産を買った第三取得者は、正当な利益を有する第三者と言えるか??
⬇︎
言える
債務を弁済すれば、抵当権は付従性によって消滅し、抵当権は実行されないため
(物上保証人、後順位抵当権者なども正当な権利を有する第三者)
(借地上に借地権者が建てた建物を借りている人も、家主が支払うべき敷地のちだいの弁済については、正当な利益/旧法上の利害関係があるとされている)
弁済の相手方
・受領権者
弁済を受ける、返してもらう側の人
債権者やその代理人など
法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者
・受領権者が弁済を受けたら
当然に債権は消滅する
・受領権者としての外観を有する者に対する弁済
受領権者としての外観を有する者とは、、、
受領権者ではないが、社会通念に照らしてそう見える者
(他人の印鑑と通帳をを持っている)
(受領証書/領収書を持っている)
そうした者に対して弁済がなされたとき、その弁済をした者が善意無過失であれば、その弁済は有効
(具体例)
債権者Aの通帳と印鑑を持参したC
債務者B銀行からお金を引き出した
このときB銀行が善意無過失の場合は、その弁済は有効
B銀行は債権者Aに対して二重に弁済する必要は無い
弁済の提供
弁済の提供とは、、、
債務者が自分の債務を履行するために必要な準備をして 債務者に対してその協力を求めること
(例)
不動産の売買の場合
・売主は土地を「引き渡す義務」と「所有権移転手続きを行う義務」を負う
・買主は「代金を支払う義務」を負う
・買主が売主に対して、「お金を用意したから受け取ってくれっ」とお金を持参して 売主の家まで行って言った場合、売主がお金を受け取らなくても 買主は弁済を提供したことになる
弁済の提供の方法2種類
1 現実の提供(債務に従って、現実に提供すること)
持参債務の場合、債務者は目的物を準備し、 それを持参して債権者の所に赴く必要がある
金銭債務は持参債務(持参しなければならない)
弁済は債務の本旨に従ったものでなければならず、一部の提供では弁済の提供にはならない
※自分振り出しの小切手→支払いの確実性がないため不可(現実の提供にはならない)
2 口頭の提供(弁済の準備をして受領を催告すること)
この口頭の提供ができるのは、
① 債権者が予め受領を拒んでいる場合
② 債務の履行について債権者の行為を要する場
弁済の充当
数個の金銭債権がある場合に、債務者からその 全額に足りない支払がなされた場合、どの債権について弁済がなされたものとするかが、弁済の充当の問題
(例)
債権者A
債務者B
・BはAから1000万円借りている(貸金債務を負っている)
・BはAに500万円の代金支払い債務を負っている
??Bが800万円を弁済したとき、この800万円はどちらの債務の弁済になるか??
⬇︎
・合意充当(AとBの合意によって充当)
当事者があらかじめどのように充当するのかを契約で定めていれば、それに従って充当される
合意充当が最優先
・指定充当
当事者間に合意がない場合、民法は両当事者の立場を考慮して公平の観点から、当事者の指定による充当(民法488条)を定めている
弁済者Bまたは弁済受領者Aの指定により、充当先を決める
※充当する順番は「費用→利息→元本」
・法定充当
法律の定めに従った充当方法
※充当する順番は「費用→利息→元本」
弁済による代位
弁済による代位とは、、、
保証人Cが債権者Aに弁済した場合、保証人Cは主たる債務者Bに対して求償できる
保証人の求償権を実行可能なものにするために、弁済をした保証人Cが債権者Aに取って代わる(保証人Cが債権者Aと同じ位置に立つ)こと
債務者Bのために弁済をしたものは、債権者Aの承諾なしに債権者に代位する
債権者Aが債務者Bに対して有していた債権や抵当権などを、保証人Cが実行できるようになる
1 正当な利益を有する者が弁済した場合
債権者に代位し、債務者に対して権利を実行できる
保証人は、弁済をしないと自身が強制執行などを受ける可能性があり、弁済をするについて正当な利益を有しているので、代位する
2 正当な利益を有する者以外の者が弁済した場合
この場合も、第三者は債権者に代位する
ただし、債権者から債務者への通知か、債務者の承諾がなければ、債務者に対抗できない
代位する人がいる旨を債務者に知らせなければならない
弁済する場所
契約(特約)で定めれば、その場所が弁済場所になる
弁済の場所の定めがない場合で「特定物の引渡し」の場合は、債権が発生した場所が弁済場所となる
特定物とは、、、
「特定の絵」などが特定物に当たる
この場合、契約場所まで取りに行くことになる
「特定物の引渡し以外」の場合、、、
当事者に別段の意思表示がないときは、債権者の現在の住所で行う
借りたお金を返す場合、債権者の現住所まで届けるのが原則
二人が互いに同種の債権を有している場合において、その2つの債権を対当額において消滅させる意思表示のこと
(例)
AはBに1000万円を貸している(AはBに対して1000万円の貸金債権を有している)
BはAに自己所有の家を売却し、その代金1000万円の代金債権を有している
??BはAに1000万円、AはBに1000万円、それぞれ現実に支払わなければならない??
⬇︎
お互いの持つ貸金債務と代金債務を帳消しにすれば、現実に1000万円を提供しなくても良い
帳消しにした方が簡便なため、相殺が認められている
自動債権と受動債権
上記の例でAからBに相殺を持ちかけた場合
AがBに対して持っている貸金債権は、自動債権となる
BがAに対して持っている代金債権は、受動債権となる
(誰が相殺するかによって自動債権か受動債権かが変わる)
相殺の要件
1 相殺適状にあること
自動債権と受動債権の両方が相殺できる状態(相殺適状)にあること
2 両者が対立した同種の目的の債務を負担していること
AがBに対して債権を持ち、逆にBもAに対して債権を持っていて、その両方の債権がどちらも金銭債権であること
3 それぞれの債権が有効に存在していること
時効が完成した債権でも、時効完成前に相殺適状になっていれば相殺できる
(例)
Aの債権の時効が完成した場合でも、Aとしては一旦は相殺適状の状態にあったのだから、自動的に帳消しになったと考えるのが自然
Aの期待を保護するため、例外的に、時効完成後の相殺が認められている
4 両方の債務が弁済期にあること
ただし、相殺しようとする者は自己の債務(受働債権)については期限の利益を放棄することができるため、自分が相手に対して持っている債務(自働債権)さえ弁済期にあれば問題ない
※期限の利益を放棄するとは、、、
相手が自分に対し、返済日がきていなくても返済を要求できるようになること
5 債務の性質が相殺を許すものであること
自動債権に抗弁権がついている場合は相殺できない
相殺を許すと、抗弁を主張できるという相手方の利益を奪うことになるため
5 当事者間に相殺禁止特約がないこと
相殺適状にあっても、相殺できない場合2つ
(1)受動債権が一定の不法行為等によって発生した債権である場合
・悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
(損害を与える意欲がある悪意)
・人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務
(例)
AはBにお金を貸している
AはBを自動車ではねて怪我を負わせてしまった
AはBに借金を帳消しにするいといって、責任を逃れようとした
→被害者Bの救済を図るために、このような場合の相殺は禁じられている
(2)自働債権が受働債権の差し押さえ後に取得された債権である場合
差し押さえの実効性を確保するために相殺が禁止されている
差し押さえの前に取得された自働債権なら、相殺できる
※差し押さえ後に債権を取得した場合でも、それが差し押さえ前の原因に基づいて生じた債権である場合は、原則として相殺できる
相殺の方法と効力
・相殺には、条件や期限をつけることはできない
??なぜか??
⬇︎
相殺は、相手方に対する一方的な意思表示によって行われ、その効力は相殺適状になった時に遡って生じる
相殺は一方的な意思表示で行われるため、それに条件をつけてしまうと相手方の地位が不安定になってしまう
そもそも相殺の効果は相殺適状時に遡って生じるので、期限をつける意味がない
民法等2−8 債権譲渡
債権譲渡とは
人に対する権利を他人に譲ること
期限前の権利を現金に替えるために必要な場合がある
(例)
A 債権者→Bにお金を貸していて、その債権をCに売った →旧債権者になった(譲渡人)
B 債務者→Aからお金を借りている →債権者はAからCに変わった
C 新債権者→AからBに対する債権を買った →Bの新しい債権者になった(譲受人)
(具体例)
住宅ローンの支払いができなくなった場合など、銀行が債権回収会社へと住宅ローン債権を譲渡する
A 銀行→Bがローンを支払わないのでC債権回収会社に債権譲渡
B A銀行のローンを借り入れている→ローンを支払う相手がAからCに変わる
C 債権回収会社→Aから債権を買取、Bから取り立てをする
・債権譲渡自由の原則
原則として、債権は自由に譲渡できる
譲渡の時点ではまだ発生していない、将来発生する債権も譲渡することができる
譲受人は発生した債権を当然に取得できる
譲渡人と譲受人との間の合意によって成立する
・例外
1 性質上譲渡できない場合
2 当事者が譲渡禁止の特約をした場合
3 譲渡制限特約がついている場合
譲渡制限特約→当事者の合意によって、譲渡を禁止し制限する特約のこと
この譲渡制限特約がある場合でも、原則、債権は移転する
(資金調達しやすいように緩和した)
※平成29年の民法改正により、債権譲渡の禁止特約の内容変更
改正前
譲渡人と債務者の間で譲渡禁止特約がある場合、債権譲渡は不可だった
また、仮に渡したとしても、債務者は弁済する必要はなかった
改正後
譲渡人と債務者の間で譲渡禁止特約があったとしても、債権の譲渡は可能になった
ただし譲受人が悪意または重過失の場合、譲受人から債務者が履行を請求されても、債務者は拒絶または、譲渡人に対して弁済することを主張することができる
(例)
A 債権者→Bにお金を貸していて、その債権をCに売った →旧債権者になった(譲渡人)
B 債務者→Aからお金を借りている →債権者はAからCに変わった
C 新債権者→AからBに対する債権を買った →Bの新しい債権者になった(譲受人)
AがCに債権譲渡をしたが、Cがその特約について悪意/重過失があった
→BはCに対して債務の履行を拒むことができる
→BはAに対して弁済等をすれば、そのことをCに対抗できる
通知か承諾のどちらかだけで足りる
・通知か承諾があれば、債務者のBは債権譲渡の事実を知っているので、AとCへの二重弁済を防ぐことができる
・通知や承諾は口頭でOK
1 債務者に対する通知
これは債権者=譲渡人しかできない
保証債務付きの債権譲渡は主たる債務者に通知すれば足り、保証人に通知する必要はない
・通知は譲渡人のAのみが行う
・CがAに代わって行う通知は認められない
※譲受人でも構わないとしてしまうと、譲り受けてもいない者が嘘の通知をする恐れがあるため
2 債務者の承諾
これは債権者=譲渡人・譲受人のどちらにしても良い
・承諾が譲渡人・譲受人のどちらにしても構わないのは、Bが今の債権者を認識していればOKだから、どちらに対して承諾しても足りる
次の1または2を満たせば足りる
- 譲渡人Aからの、確定日付のある通知
- 債務者Bからの、確定日付のある承諾
(例)
・AはBに対する債権1000万円を持っている(弁済期日9/1)
・Aはその債権をCに譲渡したあと、Dに対しても譲渡した(二重譲渡)
・弁済期日9/1が到来し、CとDはそれぞれ、Bに対して弁済を請求した
??CとDのどちらが、Bから弁済を受けることができるか??
⬇︎
CとDは第三者の関係となり、要件を満たしたほうが対抗できる
1 譲渡人Aからの、確定日付のある通知があれば対抗できる
2 債務者Bからの、確定日付のある承諾があれば対抗できる
・1か2を先に満たしている方が権利を主張できる
・通知や承諾によって、債務者Bは、AからCに債権譲渡が行われたと知ることができ、その後、DがBに問い合わせをすれば、二重に債権を譲り受けることは避けられる
・お互いが第三者に対して対抗するには、確定日付のある通知か承諾の証書(内容証明郵便など)が必要、これがない場合は対抗できない
※なぜ確定日付が必要か→後で譲り受けたDがAと共謀して、通知や承諾の前後を誤魔化す可能性があるため、これを防ぐために確定日付が必要
??CもDも確定日付のある証書による通知を得ている場合は??
⬇︎
確定日付のある通知が先に到着している方が優先される
・CとDは確定日付のある通知をBに対して送付した
・Cの送付したものが、先にBの元に到着した
・Cが優先される
??CとDからの確定日付のある証書が、同時にBの元に届いた場合は??
⬇︎
・両者とも対抗要件を備えているので、両者とも債務者Bに対して請求することができる
・Bは、CかDのどちらかに支払いをすれば良い
通知と承諾の効果
・AはBに対する債権1000万円を持っている(弁済期日9/1)
・Aはその債権をCに譲渡したあと、Dに対しても譲渡した(二重譲渡)
・弁済期日9/1が到来し、CとDはそれぞれ、Bに対して弁済を請求した
・AがCやDに、この1000万円の債権を譲渡する前に
・債務者BはAに300万円を弁済していた(債務の一部を弁済していた)
この場合Bは、譲渡人Aからの通知を受けた場合や譲渡の事実を承諾した場合には、
通知を受けたり承諾をしたりするまでに(対抗要件が備わる前に)
譲渡人Aに対して主張できたこと(BがAに300万円弁済したこと)を
譲受人のCやDに対しても主張することができる
※BはCやDに対して700万円を支払えばそれで良い
債権譲渡における債務者の相殺権
・AはBに対する債権1000万円を持っている(弁済期日9/1)
・Aはその債権をCに譲渡したあと、Dに対しても譲渡した(二重譲渡)
・弁済期日9/1が到来し、CとDはそれぞれ、Bに対して弁済を請求した
・AがCやDに、この1000万円の債権を譲渡する前に
・債務者BはAに1000万円を弁済していた(債務の全てを弁済していた)
Bは対抗要件を備えていれば、この相殺をCやDにも主張できる
(異議を留めない承諾)
異議なき承諾とは、異議があるにも関わらず、その旨を相手に伝えずに承諾すること
譲渡した債権が存在しないような場合でも、
債務者が異議無き承諾をし、相手がそれを信じたような場合は、
債務者は弁済しなければならない
(例)
・AはBからお金を借りた(BはAに対する貸金債権を持つ)
・その後、AはBにお金を貸した(AはBに対する貸金債権(反対債権)を持つ)
・BはAに対する債権をCに譲渡した
・CはAに対して「Bから債権譲渡してもらった債権を支払いなさい」と言った
・Aは「反対債権を持っているのでAB間で相殺できる、払わない」と異議を言わずに、
「わかりました支払います」と支払いを承諾した
(異議なき承諾、異議をとどめない承諾をした)
※異議をとどめない承諾をしたとしても、
新債権者Cが対抗要件を備える前に、債務者Aが反対債権を取得していたのであれば、
債務者Aは相殺をすることができる
※旧民法では、、、
「異議をとどめない承諾をした場合、Aは相殺できない」というルールだった
改正民法ではこのルールがなくなった
債権譲渡登記ファイルに記録することにより、債権者以外の第三者に対し対抗要件を備えることができる制度
確定日付のある証書による通知と同じ効果がある
この制度を活用することにより、簡単に第三者への対抗要件を備えることができる
ただし、譲渡人は法人のみ
支払いを怠っていて債権が譲渡された場合でも、必ずしも弁済する必要はない
時効が成立していれば、支払い義務はなくなる
小切手債権、約束手形債権など 6ヶ月
飲食・宿泊代金、運送料など 1年
商品の売買代金など 2年
建築工事にかんする代金など 3年
商行為に関する債権 5年
個人間の債権 10年
民法等2−7 不動産登記法
1 一不動産一登記の原則
登記記録、、、登記官が「登記簿」という帳簿に登記事項を記録したもの
一不動産一登記、、、一筆の土地、一個の建物ごとに登記記録を作成すること
2 登記機関
管轄登記所、、、不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局・支局・出張所
・管轄登記所に行けば、不動産の登記を見られる
・ある不動産が複数の登記所の管轄区域にまたがる場合、法務大臣・法務局長等が管轄登記所を指定する
3 登記記録の構成
表題部と権利部からなる
表題部(表示に関する登記)(表題登記)
表題部には「不動産を特定するための状況」が記載されている
※原則、対抗力はない
土地→所在・地目・地積
建物→所在・家屋番号・種類・構造・床面積・附属建物等
権利部(権利に関する登記)
権利部は甲区と乙区に分かれている
※原則、対抗力がある
・甲区
所有権についての記録
・乙区
所有権以外の権利(抵当権や地上権等)の記録
権利に関する登記の申請は義務ではない
所有権の登記をしない場合は表題部に氏名・住所を書き込むことになっている
この所有者を表題部所有者という
甲区に所有権登記がなされると表題部所有者の記録は抹消される
4 登記記録のサンプル

5 図面
登記所には、物件ごとの所在を明らかにするために、地図や物件所在図が備えられている
6 順位番号と受付番号
権利部に記載する2つの番号のこと
登記記録 権利部 甲区の場合
・ 順位番号
登記記録の権利部甲区に記載されている、所有権を記録した順番の番号
登記記録 権利部 乙区の場合
・ 順位番号
登記記録の権利部甲区に記載されている、抵当権や地上権を記録した順番の番号
登記記録 権利部 甲区・乙区共通
・受付番号
登記所で登記の申請を受け付けた順に振られる番号
※登記した権利の優劣は、原則として登記の前後で決まる
順位番号を見れば、優先順位がわかる
同区間の権利の優先順位は、順位番号の前後で決まる
?? 甲区に記載されている所有権、乙区に記載されている抵当権がある、抵当権の優劣はどこで判断できるか??
⬇︎
順位番号は同じ区内の中の記録の順番のため、違う区との優先順位はわからない
別区間での権利の優先関係は、受付番号で登記の受付の順番を確認すれば良い
登記記録は誰でも交付請求することができる
・手数料を納付する
原則として収入印紙、一定の場合は現金での納付も可
・登記事項証明書
登記記録に記載されている事項の一部or全部を証明した書面
全部の事項を証明するもの、現在効力を有する事項のみを証明するものなどがある
・登記事項要約書
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面
・送付を請求することもできる(郵送OK)
・電子情報処理組織を使用して請求することもできる(オンライン請求OK)
申請主義の原則
・申請主義→登記をしたければ申請する
(登記は任意、当事者の自由意志による)
・所有権移転登記などの権利に関する登記
当事者の申請、官公庁の嘱託によって行われる
※申請する義務は無い
(例外)
表示に関する登記は例外にあたる
土地が新たに生じた場合や建物の新築や滅失した場合
所有権を取得した者は1ヶ月以内に、表示に関する登記の申請をしなければならない
・職権主義
登記官が職務として登記を行うことができる
・表示に関する登記は申請する義務がある
・共同申請の原則
・登記義務者→登記をすることで所有権を失う者
・登記権利者→登記をすることで所有権を得る者
※共同申請は嘘の登記を防ぐための仕組み
(例外)
・単独申請
1 登記手続きをすべきことを命ずる確定判決による登記
(嘘の登記が行われる恐れがないので単独登記OK)
2 相続または合併による権利の移転の登記
(共同で申請することができない場合)
3 登記名義人の氏名等の変更の登記または更生の登記
4 所有権保存の登記
(共同で申請することができない場合)
5 仮登記義務者の承諾があるとき
仮登記を命ずる処分があるときの仮登記
(嘘の登記が行われる恐れがないので単独登記OK)
6 仮登記の抹消
・仮登記の登記名義人が行うもの
・仮登記の登記名義人の承諾により仮登記の登記上の利害関係人が単独で行うもの
7 起業者が行う不動産の収用による所有権の移転の登記
※登記の申請には、申請情報と添付情報を登記所に提供して登録する
・申請情報
不動産を識別するために必要な事項
申請人の氏名または名称
登記の目的などの情報
・添付情報
申請情報と併せて提供することが必要な情報のこと
1 登記原因証明情報
・登記原因証明情報→売買契約の内容を書面にした売買契約書のこと
登記の原因となった法律行為(内容)が何なのかを表す
売買によって所有権移転登記を行う場合、「売買契約」が登記の原因
実際はこの売買契約書を「登記原因証明情報」という書面に転記して登記申請する
※権利の変動に関する登記原因について嘘の登記がされないようにしている
※所有権保存登記の場合は不要
2 登記識別情報
登記義務者の本人確認ための書類
登記する際に添付する
登記権利者と登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合に必ず必要
・売買契約の場合
売主A(登記義務者)が、本当に売主なのかを確認するための書類が登記識別情報
前売主B → 売主A → 買主C
という売買の流れにおいて
AB間の所有権移転登記で、新しい所有権者Aに登記識別情報が渡される
AがCに所有権を移転する場合に、Aは「自分が真なる所有権者です」と証明するために登記識別情報を登記所に提出する
3 その他の添付情報
・代理人が登記の申請をするとき
→代理人の権限を証する情報の提供が必要
・登記原因について第三者の許可・同意・承諾を要するとき
→許可などをしたことを証する情報の提供が必要
・登記の受付
申請情報等が登記所に提供された場合、登記官は登記の申請を受理しなければならない
・登記の完了
登記が完了すると登記完了証が交付される
申請人自らが登記名義人となる場合、その登記が完了したときは、登記官はその申請人に対して、その登記にかかる登記識別情報を通知する
申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をした場合は通知されない(登記識別情報不通知制度)
1 登記の内容による分類
①所有権保存登記
所有権の登記のない不動産について、最初に行われる登記のこと
注文住宅を新築した場合・新築の建売住宅・新築マンションを購入した際に、所有権保存登記を行うことで、その建物の所有者が自分であると明示する
②所有権移転登記
既に所有権の登記がされている不動産について、所有権が売主から買主に移ったことを明確にするために行う登記
土地の購入(所有権のない土地はほぼない)や、中古住宅(一戸建て・マンション)を購入した場合の建物について行う
③変更登記
登記をした後に、登記された内容と実体との間に不一致が生じた場合に、それを変更する登記
④更正登記
登記されたときに、すでにその登記内容に錯誤や遺漏があった場合に、これを訂正する登記
⑤抹消登記
登記の記載を抹消する登記
抹消を申請する場合、その抹消について登記上利害関係を有する第三者がいるときは、その承諾がなければ申請できない
2 登記の形式による分類
・主登記
独立した順位番号を有する登記
・付記登記
独立した順位番号がない登記
主登記との同一性や順番を維持するために、主登記に付記して行われる
(登記名義人氏名等の変更の登記、買い戻し特約の登記など)
3 仮登記
・仮登記
所有権取得の順位を確保するためのもの
仮登記のままでは、原則として対抗力を持たない
(9/1に仮登記、10/1に本登記→9/1という日付の順位が維持される)
・1号仮登記
物権変動は生じているが、登記識別情報を提供できないなど、手続き上の条件がかけているときにする登記
・2号仮登記
物権変動が生じていなくてもできる登記
※仮登記の申請も原則として共同申請
※所有権に関する仮登記を本登記にする場合、登記上利害関係を有する第三者がいるときは、その承諾が必要
※ある人の本登記が完了すると、その他第三者の所有権移転登記は、登記官の職権で抹消される
(例外)
・仮登記義務者の承諾がある場合は単独申請可
・仮登記を命ずる処分がある場合は単独申請可
※処分→判決よりも簡易な裁判所の判断
4 土地の分筆・合筆の登記および建物の分割・合併の登記
①土地の分筆の登記
・分筆
1つの土地(一筆の土地)を複数の土地に分割し分けること
・分筆登記
分筆するために行う登記手続き
※区画整理地・市街化調整区域など、どのような土地においても分筆登記は可能
※分筆登記を行うには、分筆を行う土地の境界が確定していることが前提条件
※土地の境界が確定していない土地は分筆登記を行うことができない
※昔に境界を確定した場合は、再度土地の境界確定を行う必要がある
・土地を分筆したら
分筆後の新しくできた土地には新たな『地番』が付される
その土地の登記記録が作成される
その土地の「地図又は地図に準ずる図面(公図)」に分筆された境界線が加筆される
・分筆を行う目的
・土地の一部を売るため
・共有(複数の所有者で所有)する土地を分筆し、それぞれの土地を単有(1人で所有)できるようにするため
・土地を相続する際に、土地を分筆し、相続人で分けて相続するため
・1つの土地の中で、土地の一部の地目が異なり現状に合わせた登記記録にするため
・融資を受ける際に、全ての土地が担保にとられないよう、分筆し、担保に取られる土地を制限するため
・固定資産税を節税するため
・分筆登記の申請人
・所有権の登記がない不動産の表題部所有者・所有権の登記名義人
??なぜ登記がない所有者も分筆登記できるようにしたのか??
⬇︎
もし「所有権の登記名義人」しか分筆できないとすれば所有権保存登記をしていない土地の所有者が分筆できなくなってしまうから
・分筆登記に必要な書類
分筆する土地に抵当権や地役権などが付着していた場合、登記で必要な書類が試験で問われる
・担保権(抵当権、質権、先取特権)のある土地の分筆
共同担保目録を添付しなければならない
共同担保目録
同一債権の担保として複数の不動産の上に設定された抵当権を設定するための書類
今回分筆することで、分割後の数筆の土地が同一の債権を担保することになる
・地役権のある土地の分筆
地役権証明情報を添付しなければならない
地役権証明情報
・地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報
・地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
??なぜ必要か??
登記申請に地役権者が含まれていないので、地役権の存続などについて地役権者の意思確認を図るため
②土地の合筆の登記
・合筆
複数の土地を一筆の土地にまとめること
※合筆できないのはどのような場合かを重点的に覚える
・合筆の登記
登記記録上、数筆の土地を合併して1筆の土地にすること
・合筆の登記を申請できる人
合筆の登記の申請ができるのは、表題部所有者または所有権の登記名義人
(分筆の場合と同じ)
所有権の登記のある土地の合筆登記の申請は、合筆前のいずれか1筆の土地の、所有権の登記名義人の「登記識別情報」のみの添付で良い
(合筆の登記の意思確認は十分とされる)
・合筆の条件
互いに接続していない土地同士は合筆できない
公図上(地図上)でも現地(実際)でも、土地と土地が接続していること
土地と土地の接続については、土地の境界線で接していなければならない
(境界の一点だけが接していてもダメ、線で接していること)
接続している土地でも、地番区域の異なる土地は合筆できない
接続している土地でも、地目の異なる土地は合筆できない
・土地の所在
その土地が所在する市区町村及び字(あざ)のこと
「〇〇市〇〇町字〇〇」といったもの
・土地の地目(ちもく)
土地の種類のこと
「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」など
※土地の所在(地番以外)が全く同じで、地目も宅地と宅地といったように同じであれば、
合筆することができる
※地目で注意すべきこと
合筆したい土地のそれぞれの登記情報の地目が同じだけでなく、現地の地目も同じでなければならない
合筆したい2つの土地の登記上の地目が同じ宅地であっても、現地で、片方または両方の土地が宅地でないなら合筆することができないということになる
合筆しようとしている土地の登記上の地目が宅地なら、現地の地目も宅地でなければ合筆できない
3 土地の表題部の所有者又は所有権の登記名義人が同じであること
・土地の登記上の所有者の名義が同じでなければ合筆できない
合筆したい土地の所有者の登記上の住所氏名が全て同じで、現在の住所氏名とも同じでないと合筆することができない
もし、合筆しようとしている土地の所有者の登記上の住所と氏名が少しでも違っている場合は、合筆登記の前に所有者の住所や氏名の変更登記が必要
※合筆しようとしている土地が複数の所有者(共有)の場合も同じ
1筆の土地に所有者が混在すると混乱が生じるため、所有者が異なる土地は合筆できない
表題部所有者、所有権の登記名義人が相互に異なる土地は合筆できない
4 表題部の所有者又は所有権の登記名義人の持分が同じであること
・土地の所有者が複数(共有)の場合
Aの持分2分の1、Bの持分2分の1のように、それぞれの所有者(共有者)の持分が登記情報に記載されている
合筆しようとしている土地の所有者が複数(共有)の場合には、それぞれの土地の所有者(共有者)の持分が同じでないと合筆することはできない
・持分が同じである場合(合筆できる)
1番の土地についての持分
Aさん→2/3
Bさん→1/3
2番の土地についての持分
Aさん→2/3
Bさん→1/3
・持分が異なる場合(合筆できない)
1番の土地についての持分
Aさん→2/3
Bさん→1/3
2番の土地についての持分
Aさん→1/2
Bさん→1/2
※土地の所有者が1名の場合は持分は関係ない、1人しかいないので
5 互いに所有権の登記がされていない土地か、所有権の登記がされていること
・所有権の登記がされていない土地
下記の登記情報の例のように、土地の登記情報の表題部という部分に、土地の所有者の住所と氏名等が記載されている土地のこと
表題部に記載された所有者の場合、所有権の登記はされていない
土地の所有者が誰なのかのみわかるようにしている状態
・所有権の登記がされている土地
下図の登記情報の例のように、土地の登記情報の権利部(甲区)という部分に、土地の所有者の住所と氏名等が記載されている土地のこと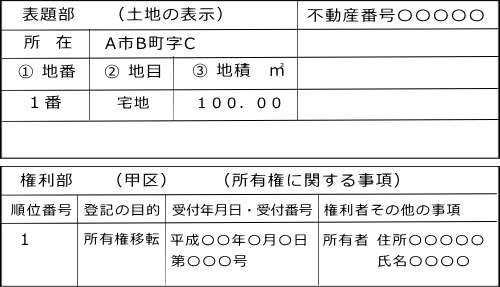
権利部の甲区(所有権に関する事項)に記載された所有者は所有権の登記をしており、
土地の所有者は誰々ですということを第三者にも対抗することができる状態になっている
※土地を合筆するためには、、、
合筆しようとしている土地がすべて、所有権の登記のされていない土地である
or
合筆しようとしている土地がすべて、所有権の登記がされている土地である
※所有権の登記のない土地と、所有権の登記のある土地を合筆することことはできない
(1筆の土地の一部についてのみ、権利に関する登記がされていることは好ましくない)
??所有権の登記のされていない土地はどうすればいいのか??
⬇︎
先に所有権の登記をしてから、所有権の登記がされている土地と合筆することができる
6 所有権の登記及び承役地の地役権の登記以外の権利登記がされていないこと
複数の土地の所有者が同じでも、それぞれの土地に所有権以外の異なる権利に関する登記がある場合は、合筆の登記はできない
所有権「以外」の権利の「範囲」が不明になるため
(例外)
・承役地についてする地役権の登記がある場合は合筆の登記が可能
(地役権がそもそも土地の一部についてでも成立するため、不都合が生じない)
※地役権
一定の目的の範囲で他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権
(公道に出るための通路/用水路から水を引く水路など)
・権利に関する登記の内で、先取特権、質権、抵当権、根抵当権の登記がある場合でも
それらの登記原因、登記の日付、登記の目的、受付番号が全て同じなら、土地の合筆をすることができる
・先取特権、質権、抵当権の仮登記がある場合も、それらの登記原因、登記の日付、登記の目的、受付番号が全て同じなら、土地の合筆をすることができる
(※根抵当権の仮登記がある場合は、どうしても受付番号が違ってくるため、合筆することはできない)
・合筆する両方の土地に、登記原因/登記の日付/目的/受付番号が同一である抵当権/質権
/先取特権の登記が設定されている場合は、合筆の登記が可能
・信託の登記であって、信託の登記特有の登記事項が同一の場合は合筆の登記ができる
土地の合筆をするには、上記の6つの条件をクリアしているかどうかを確認しなければならない
下図の登記情報の例のように、登記情報の乙区(所有権以外の権利に関する事項)の部分に記載されている
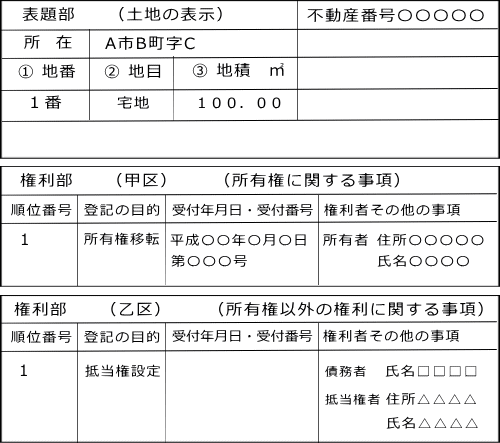
③建物の分割・合併の登記
・建物の分割登記
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されているときに、附属建物を独立した別個の建物とする場合に申請・登録するのが、建物分割登記
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物に分ける登記で、所有者の意思に基づいて申請することができる
(申請義務はない)
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割登記をする場合は相続人から申請する
この場合、相続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要
・建物の合併の登記
建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を1個の建物に合併する登記で、所有者の意思に基づいて申請することができる
(申請義務はない)
提出する登記識別情報はいずれか一方の建物のものでOK
※建物の合併の登記をすることができない場合
1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
2 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
4 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
5 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記
(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く)
民法等2−6 対抗要件 二重譲渡
誰に対して対抗するのか
(例)
AがB不動産から家を買った場合、所有権はAに移る
このとき、AとB不動産は当事者の関係になるため「対抗要件」なしで、所有権の有無を主張できる
??対抗要件が必要となるのは、誰に対して??
⬇︎
対抗するために必要な条件
B不動産がAとCに同じ家を売っていた(二重譲渡)
??この時、AがCに「家は自分が買った」と主張するために必要な条件とは??
⬇︎
家などの不動産物権変動の場合は「登記」が必要
不動産においては、先に登記を備えたものが勝ちとされている
※AやCは、引渡と登記が無ければ自分の権利を主張することはできない
民法177条の「不動産に関する物権変動は、登記法の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない
不動産の場合
・対抗要件 登記
・目的物 土地とその定着物
・原則
1 二重に譲り受けた人
2 地上権、抵当権などの物権を取得した人
3 賃借人
4 悪意者
・例外
1 不法占拠者
2 不法行為者
3 背信的悪意者
・公信力 あり
動産の場合
・対抗要件 引渡し
・目的物 不動産以外のもの
・原則
1 二重に譲り受けた人
2 地上権、抵当権などの物権を取得した人
3 賃借人
4 悪意者
・例外
1 不法占拠者
2 不法行為者
3 背信的悪意者
・公信力 なし
物権変動の外形がある以上、それに対応する物権変動があったであろうと信頼して取引に入ったものに対して、その信頼通りの効果を認める力のこと
(例)
Aが真の所有者
BはAの所有物を横領した無権利者
CはBが無権利者だと知らずに、その所有物を買った
Bは無権利者のため、Cは有効に物を取得できないのが原則となる
しかし、それではCがかわいそうな場合があるので、動産と不動産においての扱いが決められている
・動産の場合
動産は頻繁に取引される
このような場合、Cが保護されないのではかわいそう
そこで、民法はCが物を取得できるものとした
これを引渡に公信力があるという
・不動産の場合
一般に高価なものが多く、取引も動産ほど頻繁ではない
単に登記を信頼したというだけでもとの所有者が不動産を失うのは酷
そこで、民法はCは不動産を取得できないものとした
これを登記に公信力がないという
※登記の効力は絶対ではない
鉛筆にA君と名前が書いてあれば、絶対にA君の鉛筆と認めるのが公信力
不動産では、その公信力が認められていない
C君がD君の鉛筆を盗み、名前にCと記載し、先生にこれは私の鉛筆ですといった
公信力があれば、その時点でその鉛筆はC君のものになってしまう
しかし、調査を行い、実はD君の鉛筆が一本なくなっていて、そして同じ種類の鉛筆をたくさん持っている等の証拠より、実際にはD君のものだと判明した場合、名前がC君と書いてあっても、D君のものと認める、ということを現在の不動産は行っている
登記は完全に絶対ではなく、もし盗まれた登記であれば、実際に証拠等で証明すれば、真の所有者に戻るという事になる
反証によって覆る
登記の公示力とは「今誰の物なのかをわからせるための制度」
・動産の場合
持っていることが公示になる
・不動産の場合
家や土地を持って歩くわけにはいかないので、代わりに、登記が公示になる
登記には公示力があるということになる
対抗することができないとは、どういう意味か
民法177条の「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
登記をしなければ、当事者間で生じた物権変動の効果を、第三者に対して主張することができないということ
対抗要件を備えていないと、当事者から第三者へ対抗することができないが、
第三者の側から登記が備わっていない物権変動の効果を認めることは可能
登記がなくても対抗することができる第三者
登記なくして対抗することができる第三者とは、「当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺(けんけつ=不存在)を主張する正統の利益を有する第三者」ではない者を言う(大判明41.12.15)
上記の者は、不動産に関する権利を主張したいと思ったときに、登記を備えていなくても対抗できる
・無権利の名義人、およびその譲受人・転得者
Aの家を買ったB、Bは何の権利も有していないが、
この家の名義人となっているCや、Cの登記名義を信頼してCから同じ家を買ったDに対して、登記がなくとも所有権を対抗することができる
CやDは何の権利も持っていない以上「登記の欠缺を主張する正統の利益を有する第三者」ではないから
・不法行為者・不法占拠者
Aの家を買ったBは、所有権移転登記をしていなくても、不法にこの家を滅失毀損したCや不法に占拠するDに対して、損害賠償を請求して家の明け渡しを請求することができる
・転々移転した場合の前の持ち主・後の持ち主
AからBへ、BからCへと所有権が移転した場合で、登記名義はまだAにあるとする
このときCはAに登記なくして所有権の取得を主張することができる
(CにとってAは「第三者」に該当しないため)
※Aは既に無権利者となっているので、Cが登記を備えていないことを主張しても意味を成さない主張となる
BはAから所有権移転登記を得ていなくても、Cに対して所有権の取得を対抗することができる(BにとってCは「第三者」に該当しないため)
※CはBの権利に基づいて権利を取得したので、Bが登記を備えていないことを主張しても、やはり意味を成さない主張となります。
・詐欺または脅迫によって登記の申請を妨げたもの
Aが家をBとCに二重に譲渡した
CがBを詐欺や強迫することによって、Bの登記の申請を妨げた場合、
BはCが所有権移転登記を受けたかどうかに関わらず、所有権の取得をCに対抗することができる
(このような場合にBがCに対抗できないとするのは不公平であり、信義則に反するため)
・他人のために登記を申請する義務のあるもの
Aが家をB法人に売ったとする
その所有権移転登記の前にさらにB法人がB法人の代表者Cに家を売った場合、B法人はCに対して、登記なくして所有権を対抗することができる
(CはB法人の代表者として登記を申請する義務を負っていながらそれをせず、自らが家を購入し、B法人が登記を備えていないことを主張できるとするのは背信行為であり、信義則に反する)
※ただしB法人とCが二重に譲渡を受けた場合であっても、Cが先に買い受けていたときは、先に所有権移転を受けた者が対抗することができる
※他人のために登記の申請をする義務がある者とは、、、
法人の代表者、未成年の子の法定代理人、不在者の財産管理人、遺言執行者等の法定代人の他、委任による代理人など
・背信的悪意者
判例は「単なる悪意者は、民法177条のいう「第三者」に該当するので、この者に対しては登記なくして対抗できないとしている
しかし、他人が登記を備えていないことを主張することが信義則に反するような者に対してまで、登記が無ければその登記取得を対抗できないとするのは適当とは言えない
故意に人を苦しめるような悪だくみをしている人のこと
民法第177条 条文に規定
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
(例)
Aは家を購入し、登記や引渡し全般をB不動産にお願いした
しかし、B不動産はA名義で登記をせず、その地位を利用して自分の名義で登記をした
このように、他人を苦しめるような目的の人が背信的悪意者
(問)
Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。
⬇︎
解説
背信的悪意者からの譲渡人であるJ(転得者)も有効に権利を取得することができる
よって、その者自身が背信的悪意者でない限り第177条にいう「第三者」に該当する
本問Hは登記を有していない
第三者であるJに対して所有権を主張することはできない
背信的悪意者の要件事実
1 相手方の悪意
相手がわざと意地悪な気持ちを持って行動していることが第一条件となる
2 信頼を裏切ることをしたという事実があること
ただ悪意を持っているだけでは、特に問題にならない
その悪意を持って、何か他人に不利益が被るようなことをしたという事実があることが必要
以上2つの要件を満たす者が、背信的悪意者として認められる者となる
背信的悪意者排除論
「第三者」は悪意でも保護されるが、悪意者がもっぱら真の所有者の権利を害する目的でその登記の欠缺を主張する場合には、そのような主張は信義に反し、認められないとされる(最判昭和43年8月2日民集22-8-1571)
背信的悪意者排除論の論点は、第三者が背信的悪意者として認められるかどうかという点
(例)
家がAから第三者Cへ売られたことを知っているBが、その家を買った場合、
第三者Cは登記をしないと所有権をBに対抗できない
信義則に反しない限りは、Bが知っていて(悪意で)二重譲渡をした場合でも保護されるということになる
背信的悪意者の類型
多くの判例分析によれば,
(1)登記具備者が譲渡人の家族など近接した関係にある場合
(2)登記具備者が未登記の権利取得を承認し,これを前提とする行動をとりながら後に矛盾する主張をする場合
(3)登記具備者が加害目的や不当な利益取得目的で積極的に二重譲渡を教唆する場合
さらに、未登記権利者の占有や代金支払の有無, 未登記の理由,第2譲渡の無償性や対価の著しい低さなどが背信性認定の要素とされている
(疑問)
・不動産が二重売買された場合、相手方の片方が背信的悪意者であれば、背信的悪意者からの転得者は善意悪意に関わらず、保護されるのか?
⬇︎
177条の第三者は善意悪意を問和ないので、背信的悪意者からの転得者は、その者が「背信的悪意者」でない限り保護される
・「Aが甲土地をHとIとに対して2重に譲渡した場合においてHが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えた時はIがいわゆる背信的悪意者であってもHはJに対して自らが所有者であることを主張することができない」の問題で、背信的悪意者は無権利でIから買ったので、Jも無権利者ではないのか?
⬇︎
背信的悪意者というのは無権利者ではない
登記を取得しても自己の権利を対抗できないという意味にすぎない
そのため、HとJは二重譲渡の関係となる
Jが登記を取得すれば勝ちとなる
1 解除と登記 (解除した者と解除後の第三者との関係)
(例)
Aは自己所有の土地をBに売却
さらにBはCへその土地を転売
BがAに代金を支払わないので、AはBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した
この場合AはCに対して土地の所有権を主張できるか??
⬇︎
契約解除の前か後かで異なる
ケース①
AB間の売買→BからCへと転売→AB間の契約解除
この場合のCは解除前の第三者
Cが保護されるには登記が必要
AとCは対抗問題とはならない
ここで必要とされる登記は、物権変動の対抗力を主張するためではない
Cの権利を保護するための登記、権利保護要件としての登記と言われる
Cが登記をしていれば、AはCに対して土地の所有権を主張できない
ケース②
AB間の売買→AB間の契約解除→BからCへと転売
この場合のCは解除後の第三者
解除後の第三者との関係は対抗問題であるとされている
??なぜか??
・まずAB間の売買があり
・契約解除により所有権がBからAに戻り
・目的物はBからCへ売却され、所有権がCに移転した
⬇︎
これはBを起点に二重譲渡がされたことと同じ状況と考えられるから
※二重譲渡の場合の対抗要件は登記の有無
・Aは契約を解除した際に、BからAに登記を戻す機会がある
・CはBから目的物を買った時に、Cの名義に登記をする機会がある
公平に登記の機会があると考えられるので、主張できるかどうかは先に登記をしているかどうかで決まる
2 取り消しと登記 (取り消した者と取り消し後の第三者との関係)
(例)
AはBの詐欺により、A所有の土地をBに売却した
Bはさらにこの土地をCに売却した
AはBの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した
この場合、AはCに対して土地の所有権を主張することができるか??
⬇︎
前出の解除と登記と同じ結論
3 時効と登記 (時効取得者と時効完成後の第三者との関係)
取得時効によって所有権を取得した者が登場する場合
取得時効とは、、、
一定の要件を満たして、10年間か20年間、他人物を占有していると、所有権などの権利を取得できる制度のこと
ケース①
時効完成前に第三者が登場した場合
Aは登記がなくてもCに対して対抗できる
(例)
AはB所有の土地を占有し、その時効が完成した
時効完成前に、BはCにその土地を売却し、登記も移転した
Aは時効による土地の取得を、Cに主張できるか??
⬇︎
Aが時効完成により土地を取得する前に、BはCに土地を売却している
土地の所有者はC
Aの立場→時効によって土地の所有権を取得する者
Cの立場は→時効によって同じ土地の所有権を失う者
という、当事者同士の関係となる
つまりAとCの関係は対抗問題ではない
Aは登記がなくてもCに対抗できる
ケース②
時効完成後に第三者が登場した場合
登記のないAはCに対して対抗できない
AはB所有の土地の占有を続け、その時効が完成した
Aの時効完成後Bはその事実を知らないCにその土地を売却し、所有権移転登記を完了さた
Aは時効による土地の取得をCに主張することができるか??
⬇︎
Bを起点に二重譲渡が行われたと考えられる
AとCの関係は対抗問題となる
登記のないAはCに対して対抗できない
・Aは時効取得した時点で登記をする機会がある
・CもBから土地を買った時点で登記をする機会がある
⬇︎
公平に登記の機会があると考えられるので、主張できるかどうかは先に登記をしているかどうかで決まる
AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる
2 AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない
3 Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった
Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない
4 AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる
解説
1 誤り
AからB、AからCに、二重譲渡が行われている
この場合、先に登記を備えた方が所有権を主張できる
CがBに対して甲土地の所有権を主張するには、所有権移転登記を備えていなければならない(民法第177条)
2 誤り
本肢では「取消しより前にBが甲土地をDに売却」しているのでDは取消前の第三者になる
詐欺による意思表示の取消は、取消前の善意の第三者に対抗することができない(同法第96条第3項)
よって、Dが詐欺の事実を知っていた場合には、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができる
なお、Dが所有権移転登記を備えていても同じ扱いとなる
3 正しい
Bに高値で売り利益を得る目的で、Aから甲土地を購入したEは、背信的悪意者に該当する
この場合BはEに対して、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる
よって、反対にEはBに対して、甲土地の所有権を主張することはできない(同法第177条)
4 誤り
錯誤無効を主張できるのは、表意者のみ
本肢では、主張できるのはBであってAは錯誤無効を主張することはできない
また、錯誤は無効を主張するのであって、取消をするのではない(同法第95条)
疑問
?? 強迫の場合全ての第三者に対抗できるのに、なぜ登記がないと対抗できないのか??
⬇︎
BA間の売買契約締結の時期がポイントとなる
・BA間の売買が、強迫を理由とするCB間の売買契約を取り消す【前】に行われた場合
(取消前の第三者との関係の場合)
Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる
(売買がC→B→Aと流れているので、CはAに対しても主張できると考えられるから)
・BA間の売買が、強迫を理由とするCB間の売買契約を取り消した【後】に行われた場合(取消後の第三者との関係の場合)
この場合、まずBA間の売買の前に、CB間で売買契約が取り消されてる
そして、売買契約を取り消した後に、Cは法律関係を安定させるために登記をBから取り戻すべきであったにも関わらず放置しているのであれば、Cは不利益を受けても仕方ないと言える
※強迫で取り消したのであれば、ちゃんと登記も戻しておくべきだった
※Bに登記があることからAも売買を行ったのだから、Cは取り消し後に登記を放置していたリスクは負わなければならない
※AとCはBを中心として、お互いに土地は自分のものだと主張する対抗関係にある
177条に従って、登記を有する方が所有権を取得するのが妥当
??対抗要件は「不動産は登記、動産は引き渡し」となっているが、解説で「建物の賃貸借は登記がなくても、建物の引き渡しがあったときに効力を生じます」となっているものがある 建物の賃貸借は例外なのか??
⬇︎
建物の「賃借権」を第三者に対抗するときには、引渡しがあればよい
??使用貸借について「第三者への抵抗力は認められていない、引渡を受けていても対抗出来ない」とあるが、使用貸借の場合の対抗要件は何になるのか??
⬇︎
使用貸借契約については、使用借権が対抗要件をもつ方法が存在しない
つまり、借主は目的物の新所有者に対抗することはできない